この建物は瀬戸内海の島の一つである宮島の門前町にあった町屋です。建てられたのは18世紀末ごろで、二階の出窓の出格子やその下の板庇(ひさし)にその時代の特徴が見られ、屋根は勾配が緩く軒の出が深くなっています。
また、土地の狭い宮島では側壁を背中合わせに作るため、妻側の屋根の突き出しがほとんどありません。奥の座敷は明治初年に建てられた別の建物を古い建物の中にはめ込んでおり、材料を運ぶのも大変だった島の事情をよく示しています。
館内には初期伊万里から初期色絵(古九谷様式)・柿右衛門様式、鍋島様式等の名品が揃い、古伊万里の世界を一望することができます。
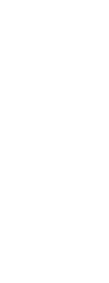
伊万里焼は今から400年ほど前に現在の佐賀県有田周辺で誕生し、近隣の伊万里港から出荷されたので、「伊万里焼」として親しまれるようになりました。時代を経るにしたがって技術が向上し、1670~90年代になると、柿右衛門様式が誕生します。この雪のように白い焼き物は、ヨーロッパの人々を魅了しました。
本展では、松濤園陶磁器館のコレクションより、柿右衛門様式の作品を中心に伊万里焼の歴史を紹介します。また、広島にゆかりのある陶芸作家の今井眞正氏の作品も紹介します。

「色絵花卉文六角壷」 1670―90年代 柿右衛門様式
学芸員が、展示内容について解説を行います。
日 時 | 2月8日(日)、3月21日(土) 11時~12時
開催場所 | 松濤園(御馳走一番館・陶磁器館)
参 加 費 | 無料(ただし、別途入館料が必要)
好きな折り紙を組み合わせてチマチョゴリを作成し、かわいいストラップに仕上げます。
日 時 | 2月11日(水・祝)、 3月20日(金・祝)、 3月21日(土) 10時~15時 ※最終受付は14時30分 (1回20~40分程度)
開催場所 | 松濤園(御馳走一番館座敷)
参 加 費 | 無料 (ただし、別途入館料が必要)

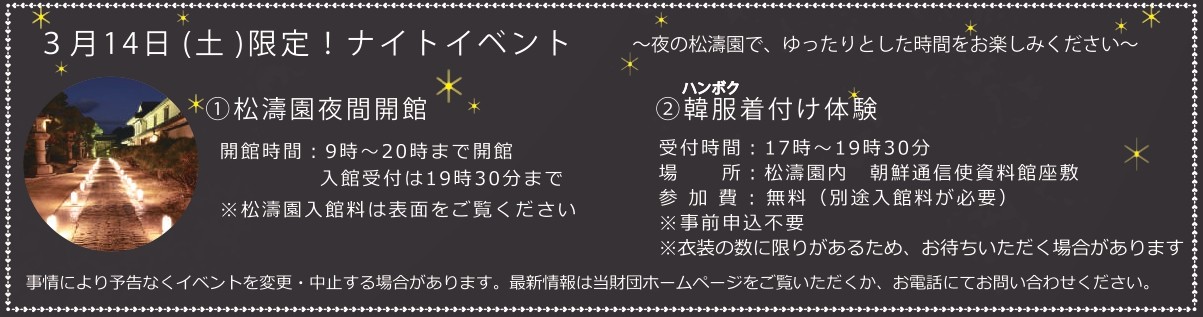
松濤園
公益財団法人 蘭島文化振興財団 松濤園 〒737-0301 広島県呉市下蒲刈町下島2277-3
TEL:0823-65-2900 FAX:0823-65-2711